適切な働き方実現に向けた取り組みとは、
組織として時間外勤務の縮減を行ったり、有給休暇取得の促進などを行うことです。
従業員の仕事と家庭生活の両立に向けた環境作りをするための取り組みともいえます。
近年多様化する労働者のニーズに対し、本人の意欲や能力を発揮できる環境や、
自ら働き方を選べる状況をつくり、「労働者にとっての働きやすさ」に着目した社会を目指します。
ワーク・ライフ・バランスが重視される背景には、次の3つの変化が挙げられます。
ワーク・ライフ・バランスが崩れると、仕事への意欲が低下し、生産性や創造性が低下してしまうことが、多くの実証的な研究によって明らかにされています。社員のワーク・ライフ・バランスを崩さないよう、また、崩してしまった場合には、その状態を早急に解消してあげるように支援することが重要となります。

ワーク・ライフ・バランスが重視され始め、それに伴い人事労務管理の考え方も変化していかなければならないにもかかわらず、従来の働き方を想定した人事労務管理制度が運用されているのが現状です。そのため、時間外労働に法的強制力のない管理職に仕事が集中し、生産性や創造性が損なわれる恐れがあります。
ワーク・ライフ・バランスの取り組みといえば、まず頭に思い浮かぶのは、短勤務時間制度や休暇制度、育児支援制度といった人事労務権利制度の改善ではないでしょうか。確かに制度を取り入れたり改善したりすることは、ワーク・ライフ・バランスを進めるために必要な取り組みといえるでしょう。しかし、実はもっと身近で簡単な取り組みにより、業務内容の効率化を行い、長時間労働が減少、年次有給休暇の取得がしやすい職場環境をつくることができます。それが、業務の「ムリ・ムラ・ムダ」をなくす取り組みとなります。内閣府が実施した調査では、「ワーク・ライフ・バランスを実現するために必要な企業の取り組み」として、約9割の人が「無駄な業務・作業をなくす」を挙げています。
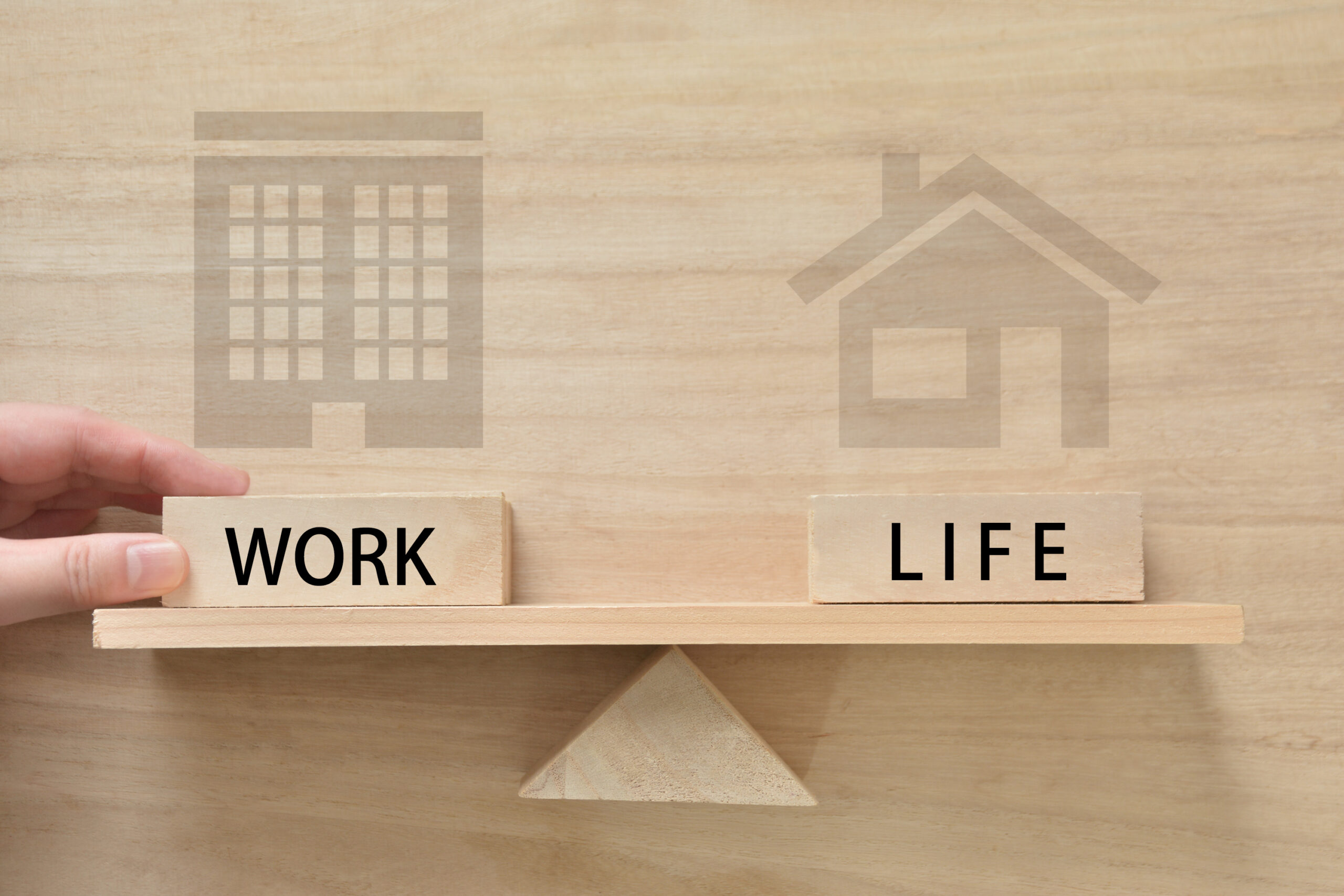
会社の仕事が効率的に行われているか等の現状を把握するため、内閣府より「10の実践」が提示されており、下記内容となります。
《工場の場合》
※株式会社あおい技研のホームページより引用しております
ワーク・ライフ・バランスの取り組みで重要なのは、両立支援等をスムーズに受け入れることのできる企業風土を社内に根づかせる等の土台づくりです。
具体的な取り組みとしては、まず様々な職位に対する研修会の開催や、組織を活性化させるためにコミュニケーションの向上につながる研修会の開催です。また、並行して業務の進め方を見直し効率化し、本来の業務遂行のために必要な時間を適正化することです。業務の効率化を行うことなく、両立支援を導入したり、「残業削減」を呼びかけるだけでは、制度が適正に利用されず形骸化する恐れがあります。
現在、厚生労働省では様々な組織を活性化させるためにコミュニケーションの向上、業務の進め方を見直し効率化につながる研修会のためのツールを提供しています。義務感からの活動では、「忙しいから」などで活動半ばで頓挫しがちです。皆で楽しめる活動にしていくことが望まれます。

《組織活性化のためのツール》
職場環境のチェックリストを基にグループ討議を行う検討会になります。職場の良い点、改善点を発表し、改善計画を作成します。期限を決め、改善内容を実施し、成果を報告します。
ストレスチェックの回答を基にした「職場の強みチェックリスト」より、職場の強みを位置付けます。その後、参加型討議により、伸ばしたい強み、職場のありたい姿を発表し合い、活動計画を作成します。いきいきとした職場づくりには、職場の弱みよりも強みに注目して伸ばす視点が役立ちます。
ご予約・各種お問い合わせ
治療のご相談やお問い合わせはお気軽にどうぞ